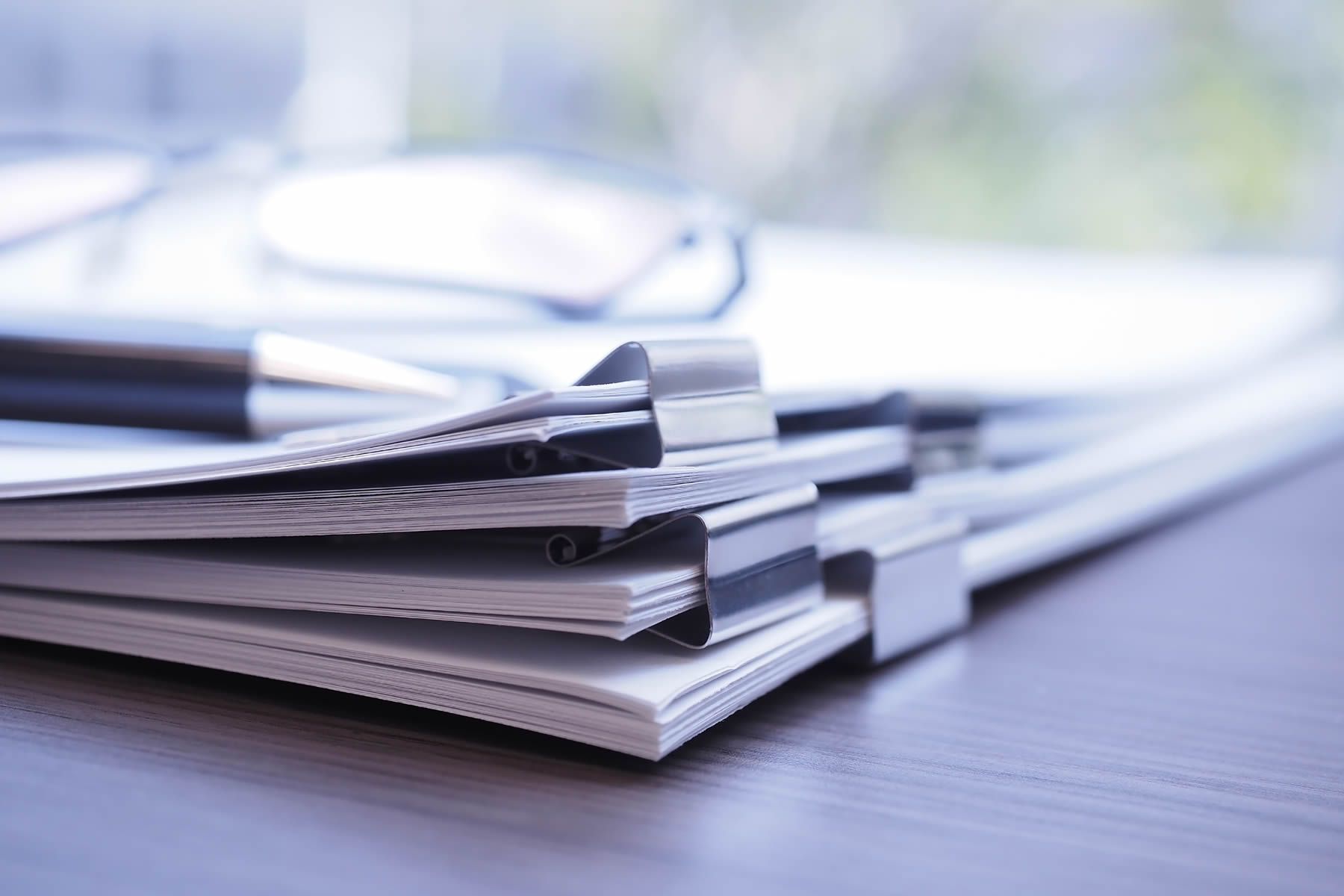(一財)消防科学総合センター
御嶽山の噴火に係る災害現地調査
2014.10
平成26年9月27日11時52分頃に発生した御嶽山噴火について、一般財団法人消防科学総合センターでは長野県大滝村及び木曽町での災害現地調査を10月3日に行いました。
近年の御嶽山の主な活動としては、昭和54年10月28日に水蒸気爆発が観測されています。また、昭和59年9月14日には王滝村直下を震源とした長野県西部地震が発生しています。
<位置図>
※背景地図は国土地理提供のものを使用。
御嶽山は長野県と岐阜県の県境付近にあります。東側には古くから中山道が南北に伸び、宿場町として栄えていました。現在は、国道18号線及びJR中央西線が走っています。
<写真①:王滝村役場>
|
王滝村役場の庁舎。この2階に災害対策本部が設置された。王滝村は人口900人弱。 |
王滝村役場前。関係機関や報道などの車が行き来した。駐車場は少なく役場職員が整理にあたっていた。 |
|
役場1階の様子。災害対応に加え、通常の業務も行われていた。 |
役場2階の災害対策本部室内部の様子。定期的に会議は行われ、自衛隊、消防、警察等も参加していた。 |
|
役場玄関前の掲示。報道機関の節度ある取材を促す新聞記事と張り紙。 |
役場周辺は、普段の生活が営まれており、車両に対し子供や高齢者に注意する旨の看板も見られた。 |
<写真②:おんたけスキー場>
|
村役場から御嶽山へ向かう途中におんたけスキー場がある。今回の噴火によりここから入山規制となった。 |
入山規制のゲート付近には多くの報道機関が集まっていた。ここから山頂まで徒歩なら3時間程を要する。 |
|
付近は、救助活動にあたる自衛隊、消防、警察の活動拠点がある。山頂付近への移動はヘリも使われた。 |
緊急消防援助隊の活動拠点。施設毎に都県隊に分かれ待機しており、中では活動準備が進められていた。 |
|
道はスキー場を過ぎ登山口で行き止まりとなっており通過交通は無い。途中の立ち入り規制の看板。 |
スキー場付近は標高2,000m以上あり、役場から現地に至る道は、長く坂やカーブが多い。 |
<写真③:木曽広域消防本部>
|
木曽広域消防本部、地域の常備消防の拠点であり、当初は県内応援や緊急消防援助隊の集結場所となった。 |
この執務室に県内応援や緊急消防援助隊が詰めたが、他機関との連携のため、大滝村役場に拠点を移した。 |
<写真④:木曽町役場>
|
木曽町役場駐車場。来訪者が多く、報道関係者と家族の車両を振りわける交通整理にあたっている。 |
木曽町災害対策本部。正面玄関と入口を別にして、災害対応用の出入り口を確保し、対応を行っていた。 |
|
木曽町役場の正面玄関。通常業務について、災害対応と入口を区別し、対応を行っていた。 |
報道関係者の立ち入りを制限するゲート。多くの報道関係者は、ゲート前で待機している。 |
<写真⑤:旧町立上田小学校>
|
廃校となった旧町立上田小学校。犠牲者の仮設の検視所と遺体安置所として使用されていた。 |
旧町立上田小学校前には、警察官が待機しており、厳重な警備を行っている様子であった。 |
<【参考写真】:長野県消防応援活動調整本部>
|
長野県庁に設置された、長野県消防応援活動調整本部の入口の様子。内部は非公開。 |